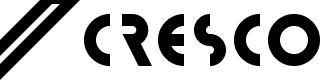DX化の前に“現場を整える” ― クレスコが教える5Sの真価
今回のコラムでは、弊社の企業文化として根づいている「5S」についてご紹介します。
5Sは「始めやすい業務改善」として多くの製造業で取り組まれていますが、実は継続こそが最も難しく、奥深い改善活動です。
「そもそも5Sとは何か」。そして、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえでも欠かせない取り組みであることをご存じでしょうか。弊社がどのようにして5Sを単なるルールではなく文化として根づかせたのか――その方法と考え方を、今回のコラムでお伝えします。
1.5Sとは ― 製造業の基盤をつくる活動
製造業における「5S」とは、**整理(Seiri)・整頓(Seiton)・清掃(Seisou)・清潔(Seiketsu)・しつけ(Shitsuke)**の頭文字をとった言葉です。単なる“片付け”ではなく、現場の秩序を生み、経営の土台を強化する取り組みです。
まず、5Sには分かりやすい顕在的メリットがあります。
・業務効率化:必要なものがすぐ見つかり、探すムダを削減。
・不要在庫の削減:不要品を把握・処分することでコスト圧縮。
・空間の有効活用:安全で作業しやすいレイアウトが可能に。
・文化醸成:整った現場は自然と改善意識を育てる。
・環境改善によるイメージアップ:清潔な工場は顧客・求職者からの信頼を高める。
さらに、見えにくいが大きな価値を持つ潜在的メリットもあります。
小さな改善を積み重ねることで、社員が成功体験を得る。
改善を「褒める文化」が根づくことで、現場のエンゲージメントが高まる。
経営層が目に見える成果を評価することで、人材育成とモチベーション向上につながる。
5Sは「環境をきれいにする」活動ではなく、社員の成長と組織の競争力を生むプラットフォームなのです。
2.DX推進の前提は「5Sができているか」
今、製造業でもデジタル化(Digitization)・デジタライゼーション(Digitalization)・デジタルトランスフォーメーション(DX)が叫ばれています。
しかし、DXを成功させるには、まずリアルの5Sができていることが前提条件です。
DXとは「必要なデジタル情報を、指定の場所に整理・蓄積し、効率的に処理すること」です。言い換えれば、情報の5Sです。ただし、デジタルの世界はモノのように手に取れず、可視化が難しいため、リアルの5Sより管理が難しいのが実態です。たとえば現場の物理的な整理整頓すら徹底できていない会社が、複雑なデータやシステムを管理しきれるでしょうか。リアルな5Sを習慣化できていない組織は、デジタルの5S=DX推進でつまずきやすいと思うのです。
3.クレスコの5S活動 ― 楽しく続ける仕組みづくり
クレスコは、**「脱6K職場」**というビジョンを掲げています。
ここでいう6Kとは、なくすべき3K(きつい・汚い・危険)と、アップデートすべき3K(勘・気合・根性)のこと。脱6K職場を達成して、働きたいと思える職場環境を自らでつくる――これが私たちの経営指針です。
このビジョンを実現するための基盤が、5S活動の徹底と文化化です。
定期チェックで「見える化」と「称賛」を両立
クレスコでは、3か月に1度、全社を15チームに分けて5Sチェックを実施しています。
診断員は社長・製造部長・他チームの担当者が務め、トップの関与と現場同士の学び合いを両立しています。
チェック内容は以下の通りです。
・前回の指摘事項が改善されているか
・エリアのゴミや不要物がないか
・改善事例の取り組み度
・定置管理(モノの置き場所が明確か)
・歩行エリアに障害物がないか など そして、必ず1つは良い点を褒めるのがルール。
これにより、単なる指摘の場ではなく、モチベーションを高める場になっています。
◎「ご褒美」と「表彰」で継続を後押し
年4回のチェックのうち3回以上で80%の達成率をクリアしたチームには、
会社負担でランチに行けるご褒美があります。
さらに、新年度の方針発表会では前年度の最優秀5S改善賞を表彰。
競い合いながらも楽しく続けられる仕組みが、5Sを単なるルールから企業文化へと昇華させています。
まとめ
5Sは、単なる整理整頓ではありません。
現場の効率化・人材育成・文化づくり・DX推進・創造力の育成まで、企業の競争力を支える土台です。
クレスコでは、楽しみながら継続できる仕組みを取り入れ、5Sを「文化」として育てています。
DXや新たな価値創造を目指す今こそ、5Sを経営の中心に据える意義を、改めて見直してみませんか。